こんにちは、カービーです。
「どうする家康」で描かれた徳川家康の正妻、瀬名が命を絶った築山殿事件。
それと並行して長男信康も切腹という悲しい最期を迎えています。
僅か21歳という若さで、父に命じられて自害するという何ともやりきれない出来事でした。
その信康の切腹の地が浜松市天竜区二俣にある二俣城、
墓所のあるのが城跡近くの清瀧寺信康廟。
信康を静かに偲べる場所、二俣城址と清瀧寺についてお伝えします。
信康の生涯
信康は1559年4月13日生まれ、1579年10月5日没の享年21歳。
家康の長男として駿府で生まれ幼名は竹千代。
今川氏の人質として幼少期を駿府で過ごすも、桶狭間の戦いの後で人質交換によりようやく岡崎城の家康の元に移ります。
1567年に信長の娘である五徳と幼くして結婚し、家康が浜松城に移った1570年には岡崎城主に。
その後長篠の戦いなどで軍功を挙げ、若くして勇猛ぶりを発揮します。
しかし妻の五徳が信長に送った十二ヶ条の訴状で瀬名と信康の罪を訴え事態は暗転。
怒った信長は家康に対して信康の切腹を命じ、幽閉されていた二俣城で最期を遂げます。
十二ヶ条の訴状の経緯 ☞ https://jumblekirby.com/tsukiyama-jiken/#toc3
信康自害の二俣城は堅固な要衝
主が入れ替わった二俣城の歴史
二俣城は現在の浜松市天竜区二俣、天竜川と二俣川に挟まれた丘陵の上に作られた山城。
築城年は16世紀前半~半ばと推測され、廃城は1600年で僅か数十年の間だけ存在。
短い歴史にもかかわらず激しい奪い合いが繰り返され、城の支配は
今川→徳川→武田→徳川
と移り変わります。
元々の二俣城の起こりは今川氏がこの地に拠点として築いた城館。
その後1569年に今川氏は滅亡し、二俣城は家康の管轄下に入る。
ところが3年後の1572年には武田信玄の大軍が南下、勝頼を大将として二俣城を落とす。
(これが三方ヶ原の戦いに繋がる)
長篠の戦いで武田軍が大敗すると今度は家康が攻める側となり、1575年末(武田入城から3年後)に二俣城を奪い返す。
3年毎に主が入れ替わるほど、名将たちが欲した重要な要衝だったということでしょう。

堅固な守備力
二俣城の奪い合いはいつも長く激しい戦いとなりました。
城は立地の良さで自然の要塞と化し、武田が落とした際も、家康が取り戻した際も、強固な守備力で容易には攻略を許さなかった。
武田は攻めあぐねた末に、二俣城から天竜川河畔に井戸櫓(いどやぐら)を築いて水を確保しているのを見つけ、
天竜川に大量のいかだを流して井戸櫓にぶつけて破壊、水の補給を絶ってやっとのことで開城させています。
家康が取り戻した際にも約7か月の攻防を経ても膠着状態が続き、
最終的には交渉によって城兵の安全な退去を条件に開城させている。
二俣城は堅固な守備力を発揮した強い城だったことが窺えます。
二俣城址を訪ねる
二俣城は今や天守台、石垣、土塁、堀の遺構が残るのみですが、城跡は国の史跡に指定されています。
城址公園の入口の駐車場に車を停めて坂を上っていくと、途中には堀切や石垣の跡が点在。
樹々の隙間からは眼下に天竜川を覗くことができます。


そのまま進むと城の北曲輪(防御用に仕切られた囲い地)跡に、明治時代に建てられた日清戦争の戦死者を追悼する旭ヶ丘神社。

さらに進むと丘の最上部に位置する天守台のある本丸跡に出ることができます。
本丸跡は南北に約50m、東西に40mで周囲を樹々で囲まれた広場になっていて、意外とこぢんまりとした印象。
その東端には野面積みの石垣で囲まれた高さ4.6m、広さ45坪ほどの天守台でこちらもとても小ぶり。
城跡への訪問客はまばら(大河ドラマ効果はここには波及せず?)で辺りは本当に静か。
天下人家康の嫡男が幽閉され自害させられた、そんな大事件が起きたとはとても思えない穏やかな場所。
この地で信康が何を考え死んでいったのか、21歳の若さで色々な経験ができる未来が待っていたはずでは、などと想像すると切ない気持ちになってきます。
二俣城址所在地: 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣990



信康が弔われている信康廟のある清瀧寺
二俣城から500mほど北東に行くと、本田宗一郎ものづくり伝承館の横に諏訪神社があり、
そこから池を右手に見ながら坂を上っていくと信康山清瀧寺があります。

清瀧寺所在地:静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1405
信康を供養する清瀧寺
本来なら家康の嫡男として二代将軍になっていたはずの信康が無念の切腹。
その信康を供養するために家康が命名・建立した寺が「清瀧寺」で、山号にはそのまま名前をとって「信康山」。
信康の首は切腹を命じた信長の元に送られ(首検めのため)、その後岡崎の若宮八幡宮に葬られています。
つまりここに眠る信康の身体には首がなく、戦国時代の非情を感じ胸が痛みます。
信康廟は静かにたたずむ
寺の山門をくぐって鐘楼を超え、右手に本堂を見ながら奥に行くと墓地が広がっています。
その中央にある階段を160段ほど登ったところに、信康を祀る信康廟。
二つの門を構えた立派な廟ですが、奥の赤い門は閉ざされたままで中を見ることは出来ません。
人の出入りもほとんどない、樹々に囲まれた場所にたたずむ廟に信康は静かに眠っています。





清瀧寺には二俣城から移築された井戸櫓
清瀧寺には二俣城のものを移築したものとも伝えられる井戸櫓があります。
天竜川の断崖に築かれた二俣城で水を確保するために設置した命綱の井戸櫓。
武田軍が二俣城攻めで壊したもので、明治時代に改築され原形とは変わっているとの説もありますが、井戸櫓がどんなものかは一目瞭然です。

寺に伝わる本田宗一郎のエピソード
清瀧寺の鐘には本田宗一郎(本田技研の創業者)にまつわる面白いエピソードが伝わっています。
”宗一郎が二俣尋常高等小学校(現在の二俣小学校)に在学中のある日、
「腹が減った」
と授業中に教室から抜け出し裏山の清瀧寺へ。
宗一郎は定刻の30分前に寺の鐘を突き、昼食時間を前倒ししてまんまと弁当を早く食べた!”
これは清瀧寺の歴史の一部として、寺の鐘楼前の掲示版で紹介。
いかにもやんちゃな宗一郎らしい人柄が伝わる話ですね。

まとめ
家康の嫡男、信康が切腹をした二俣城と信康を供養する清瀧寺。
浜松市天竜区にある信康にまつわる二つの場所は、
身内であっても命を見捨てた激烈な戦国時代と、
この地に散った信康に思いを馳せられる静かな場所です。
浜松市街からは車で1時間ほどの距離にありますが、
すぐそばには秋野不矩美術館や本田宗一郎ものづくり伝承館もあって、
あわせて一日観光をすれば本物の歴史・芸術・産業に触れることができます。
ご家族で、ご友人と、あるいはお一人でも楽しんでみたらいかがでしょうか?

秋野不矩美術館情報 ☞ https://jumblekirby.com/akinofukumuseum/
本田宗一郎ものづくり伝承館情報 ☞ https://jumblekirby.com/honda-museum/
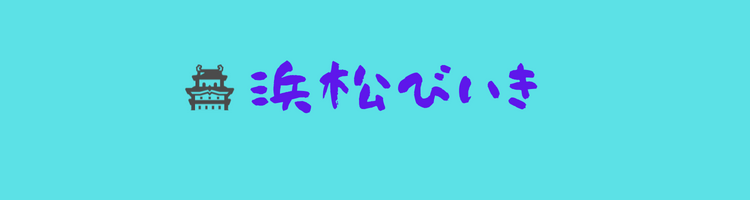



コメント